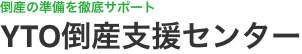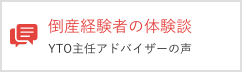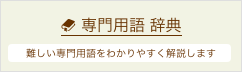-
相続放棄とは…
- 相続人が相続を放棄することです。
- 相続放棄をすると相続人はプラスの遺産もマイナスの遺産も一切相続をしないことになります。
相続放棄について知っておきたいこと
- 相続放棄には期限があるため、注意が必要です。
- 相続人が亡くなった日から3か月以内でなければ相続放棄の手続きはできません。
- 相続人が亡くなった日から3か月以上経過した場合、相続放棄の手続きはできなくなります。
YTOからのアドバイス
- 破産手続きに際して破産申立人が亡くなった場合、相続人にプラスの遺産とマイナスの遺産の双方が相続されます。
- 特にマイナスの遺産の被相続人の保証債務には注意が必要です。
- 亡くなった破産申立人が保証人となっている債務がマイナスの遺産として相続されるからです。
- 債権者は遺産分割協議書の提示を求めて被相続人の保証債務の相続状況を確認します。
- この点にも注意が必要です。
- 相続放棄の手続きを行うとマイナスの遺産の相続は回避できます。
- ただし相続放棄には期限(3か月以内)があるため、注意が必要です。
試算表とは…
- 決算の確定前に「仕訳帳から総勘定元帳の各勘定口座への転記が正確に行われているか?」を検証するため、複式簿記の前提である貸借平均により作成する集計表のことです。
- 試算表には合計試算表・残高試算表・合計残高試算表の3種類があります。
- 借方と貸方の最終的な数値が一致した場合に「正しい」と認められます。
試算表について知っておきたいこと
- 決算後6か月以上が経過している場合、借入に際して金融機関から試算表の提示を求められることがよくあります。
- 試算表が破産手続きの際に問題になるケースがあるため注意が必要です。
- ⇒試算表の粉飾による借入が問題になるケースがあるため注意が必要です。
YTOからのアドバイス
- 決算後6か月以上が経過していて借入に際して金融機関から試算表の提示を求められた場合、「倒産直前で資金繰りに困っているから」と試算表の売上勘定・売掛金勘定を粉飾して借入してしまうケースがあります。
- この借入が「粉飾による詐欺まがいの借入である」と疑われた場合、破産管財人に調査させる可能性があります。
- 破産管財人の調査により「詐欺による借入である」と判断された場合、免責不許可事由となり免責が認められなくなるため注意が必要です。
- もし倒産直前の借入に『試算表の粉飾による借入』がある場合には事前に対策を講じる必要があります。
資産とは…
- 「将来収益をもたらす」と期待されるものを言います。
- 資産は①それ自体に価値があるもの(現金・有価証券・建物・土地等)と②それ自体に価値がないもの(繰延資産・前払費用等)の2つにわけられます。
資産について知っておきたいこと
- 破産申立時、資産は資産目録で報告する必要があります。
- 資産は①法人資産と②個人資産にわけて報告する必要があります。
- 漏れが多々あるなど資産の報告が不適切な場合、破産管財人に資産隠しを疑われる可能性があるため注意が必要です。
YTOからのアドバイス
- 資産目録で報告する代表的な資産は以下のとおりです。
- 現金預金
- 有価証券
- 保険
- 土地・建物(不動産)
- 車(動産)
- 資産目録では①法人資産と②個人資産のそれぞれを報告する必要があります。
- ちなみに『過去5年間における購入価格が20万円以上の物品』も資産として報告しなければいけません。
- この報告が漏れた場合、破産管財人に調査される可能性があるため注意が必要です。
債権回収とは…
- 期限までに支払われなかった債権を回収するため、債権者が講じる法的手段等のことです。
- 一般的には日常から生じる債権(未収金債権・料金債権等)が回収されます。
債権回収について知っておきたいこと
- 債権回収は『期限までに支払われなかった債権の回収』であるため、一般的に債権者は法的手続きによる回収を行います。
- ⇒弁護士からの差押え・未払い金請求訴訟・強制執行等の法的手続きで回収を行います。
- この場合、資産・現金預金等が法的手続きの対象となるため注意が必要です。
YTOからのアドバイス
- 債権回収は差押え・未払い金請求訴訟・強制執行等の法的手続きであるため、突然行われることはありません。
- 事前の協議等で債権者が「債権を回収できない」と判断した時に行われることが一般的です。
- 突然行われる訳ではないため、事前の対処が可能です。
- ⇒破産申立・免責申立等に影響が出ないよう事前に対処する必要があります。
- ⇒破産申立・免責申立後の生活費の準備等に影響が出ないよう事前に対処する必要があります。
償還免除申請とは…
- 公的な借入金(緊急小口資金等)の償還時において、一定の条件を満たすと返済が不用になる特別措置です。
償還免除申請について知っておきたいこと
- 公的な借入金(緊急小口資金等)の償還時に以下の条件を満たすと適用されます。
- 償還期限においてもなお、所得が減少している場合。
- 償還期限においてもなお、住民税非課税世帯となっている場合。
YTOからのアドバイス
- コロナの影響による公的な借入金(緊急小口資金等)にも償還免除申請をおこなえます。
- ただし償還免除申請の承認には以下が必要になります。
- 償還時においてもなお、所得が減少していることの証明。
- 償還時においてもなお、住民税非課税世帯であることの証明。
- 償還免除申請は一定の所得がない方の権利です。
- 償還免除申請は躊躇せずに申請をしても差し支えありません。
- 償還免除申請は破算申立(倒産)の準備中に申請をしても差し支えありません。
- 償還免除申請が承認されれば破産申立(倒産)の準備中に返済をする必要がなくなります。
住民税非課税世帯とは…
- 住民税が課税されない世帯のことです。
- 住民税は年間所得が一定以下等の場合に非課税となります。
住民税非課税世帯について知っておきたいこと
- 単身世帯の場合:年間の所得が45万円以下
- 一人親・障害者世帯等の場合:年間の所得が135万円以下
YTOからのアドバイス
- 破産申立後でも年間所得が一定額以下の場合には住民税非課税世帯を申し出ても差し支えありません。
- この申し出は最寄りの行政で手続きをおこなうことになります。
- 住民税非課税世帯と認定されると国民健康保険料・介護保険料・高額医療制度を受ける際の自己負担額等で優遇措置を受けられます。
相続放棄とは…
- 被相続人の財産に対する相続権を放棄することです。
- 被相続人のすべての財産が放棄の対象となります。
- 預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、負債などのマイナスの財産も含まれます。
相続放棄について知っておきたいこと
- 相続を放棄した場合、相続人はプラスの財産もマイナスの財産もいずれも承継できません。
- プラスの財産だけの承継はできません。
- マイナスの財産だけの放棄はできません。
YTOからのアドバイス
- 破産申立をした際に相続手続きが発生している場合、相続財産は資産として裁判所に報告をしなければいけません。
- 相続手続きが完了するまで破産手続きはできなくなります。
- ただし相続放棄をすれば破産手続きは進められます。
- 相続放棄は「相続人である」と本人が知った日から3か月以内に申し出なければいけません。
- 3か月を経過すると相続放棄はできなくなります。
- 注意が必要です。
相続とは…
- 死亡等の事情により、その人の法律関係を中心とする財産上の地位を受け継ぐことです。
- 死亡等の事情により、その人のさまざまな権利・義務を包括的に受け継ぐことです。
- 主に親族関係にある者が受け継ぎます。
相続について知っておきたいこと
- 破産申立の際に相続手続きが発生している場合、その相続財産は破産申立時に報告する資産に該当します。
- 相続財産は資産目録に計上し、裁判所に報告をしなければいけません。
YTOからのアドバイス
- 相続手続きが発生している場合、相続手続きが完了するまで破産申立はできなくなります。
- 破産申立時に相続手続きが生じた場合、破産管財人は相続財産を差押えします。
- 破産申立時に相続手続きが生じた場合、相続財産を報告しなければいけません。
- 報告を忘れると資産隠しを疑われますので注意が必要です。
財務諸表とは…
- その会計年度における会社の利益・損失の内容・会社の財政状況の内容を報告するための書類です。
- 財務諸表は会計規則上の呼称です。
- 財務諸表は一般的には「決算書」と呼ばれます。
財務諸表について知っておきたいこと
- 財務諸表は貸借対照表と損益計算書から構成される会計規則上の書類です。
- ⇒貸借対照表には、資産と負債の内容が記載されます。
- ⇒損益計算書には、売上総利益・営業利益・経常利益・税引前当期純利益・当期純利益の内容が記載されます。
- 財務諸表では上記により会社の業績等を正確に報告することが義務付けられています。
- 意図的に正確に報告をしない場合には粉飾決算として問題となることがあります。
YTOからのアドバイス
- 財務諸表は会社の経営状況・会社の経営実態を正しく把握するための書類です。
- そのため1会計年度ごとの作成が義務付けられています。
- 破産申立時には直近2年度分の財務諸表の提示が義務付けられます。
- 破産申立時に決算をしていない場合(未決算状態)、破産申立が受理されない可能性があります。
- 注意が必要です。
- また粉飾決算をしている場合、破産管財人により粉飾決算の状況を調査されることになります。
- 注意が必要です。
就業規則とは…
- 事業者ごとに作成が義務付けられている雇用主と従業員との間の雇用に関するルールです。
- 常時10人以上の労働者を使用する雇用主は就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署に届け出る必要があります。
就業規則について知っておきたいこと
- 就業規則は会社ごとではなく、事業場(支店や店舗)ごとに作成します。
- そのため会社全体に10人以上の従業員がいたとしても、各事業場(支店や店舗)の従業員が10人未満の場合には就業規則を作成する義務はありません。
YTOからのアドバイス
- 破産申立をした場合、破産管財人から就業規則の提示を求められることがあります。
- 従業員に対しての未払い賃金・未払い賞与・未払い退職金・未払い残業代等がある場合です。
- 従業員に対しての未払い賃金等がある場合、破産管財人は未払い賃金立替払い制度の利用を準備します。
- この時に就業規則の確認を求められることがあります。
- 破産管財人が就業規則の規則内容等を確認する必要があるからです。
- 就業規則は労働基準法で作成と届け出が義務付けられているため、破産管財人から就業規則の提示を求められた時に困らないよう準備しておく必要があります。
タップで発信アドバイザー直通電話