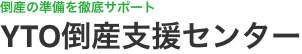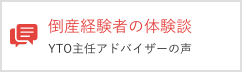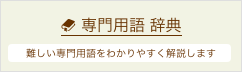-
出資金とは…
- 会社などの組織が事業などを行う上で必要な資金を調達する方法の1つです。
- 企業理念などに賛同する人が会社の成長を見込んで提供するするお金のことです。
出資金について知っておきたいこと
- 出資金は資産になります。
- 出資金は破産管財人の調査によって回収が可能となる財産に当たります。
- 破産申立時に出資金は法人資産と個人資産に分類し、資産目録に計上して報告する必要があります。
YTOからのアドバイス
- 破産申立時に報告する必要がある主な出資金は以下の通りです。
- 株式会社が発行する株券
- 信用金庫が発行する出資証券
- 信用組合が発行する出資証券
- ETC事業者が発行する出資証券
- 上記の出資金は破産管財人が必ず調査をします。
- 出資証券を準備した上で資産目録に計上して報告する必要があります。
資産譲渡とは…
- 将来収益をもたらすと期待される資産を、その同一性を保持しつつ有償または無償で他人に譲渡することです。
資産譲渡について知っておきたいこと
- 資産譲渡の主な対象は動産・不動産です。
- ⇒動産とは車・物品等です。
- ⇒不動産とは土地・建物等です。
- そのほかにも現金・有価証券等も資産譲渡の対象となります。
YTOからのアドバイス
- 破産申立時の資産譲渡は破産管財人による調査対象となります。
- 一般的に直近2年前までの資産譲渡が調査対象となります。
- 調査対象となる代表的な資産譲渡は以下の通りです。
- 現金・有価証券の譲渡
- 土地・建物の譲渡
- 車・物品の譲渡
- 不適切な資産譲渡と判断された場合、破産管財人から返還等を命じられる可能性があります。
- 注意が必要です。
再リースとは…
- 契約にもとづいてリース期間満了後もリース資産の使用を継続することです。
再リースについて知っておきたいこと
- リースの継続(再リース)には再リース料の支払いによる更新手続きが必要です。
- 再リースの手続きは年額基本リース料の1/12程度を再リース料として支払うことが一般的です。
- 再リースの手続きは更新事項として契約に盛り込まれていることが一般的です。
YTOからのアドバイス
- 倒産をしても再リース資産(車・パソコン等)を継続使用することは可能です。
- ただし一定評価額以下の再リース資産(車・パソコン等)に限られます。
- また再リース資産(車・パソコン等)を継続使用するための手続き履歴や再リース料の支払い履歴を破産申立時に破産管財人に報告して許可を得る必要があります。
生活保護受給権とは…
- 生活保護法により規定され、憲法で保障されている健康で文化的な最低限度の生活を維持するために生活保護を受ける権利のことです。
生活保護受給権について知っておきたいこと
- 生活保護受給権は国が定める保護基準に満たない場合に生活保護費の支給を受けることができる権利です。
- 生活保護受給権は破産申立に際して制限を受けることはありません。
- 破産申立をしても生活保護受給権により支給される生活保護費は受け取ることができます。
YTOからのアドバイス
- 生活保護受給権にもとづく生活保護費は破産申立をしても受け取ることができます。
- 生活保護受給権は差押禁止財産に当たるため、破産申立をしても制限を受けることはありません。
- ただし負債のある金融機関の口座を生活保護費の受取口座にしている場合、破産申立時の差押によって支給された生活保護費を受け取れなくなります。
- 注意が必要です。
差押禁止財産とは…
- 破産財団の構成にならず、換価の対象にもならない財産です。
- 破産者が手元に残すことができる財産です。
差押禁止財産について知っておきたいこと
- 差押禁止財産は強制執行においても差押が禁止されている財産です。
- 破産申立前に、差押禁止財産を手元に残すための準備をしておく必要があります。
- 差押禁止財産も準備をしないと手元に残せない場合があります。
- 注意が必要です。
YTOからのアドバイス
- 破産申立の際に手元に残すことが認められている差押禁止財産は以下の通りです。
- 生活に欠くことのできない家財
- 生活に必要な食料・燃料
- 退職金請求権の4分の3
- 破産後に得た給料
- 生活保護の受給権
- 年金の受給権
- 子供手当の受給権
- 差押禁止財産を手元に残す場合、状況を破産申立時に破産管財人に報告する必要があります。
- 差押禁止財産を手元に残す場合、状況を報告できるように事前に準備しておく必要があります。
自由財産とは…
- 破産手続きにおいて破産財団に属さず、破産手続き後も所有することのできる財産です。
- 破産者が自由に管理・処分できる財産です。
自由財産について知っておきたいこと
- 破産手続きにおいて財産をすべて取り上げられてしまうと、破産者は生活ができなくなってしまいます。
- そこで破産申立後の破産者の生活再建を図る目的で所有することが認められている財産があります。
- その財産が自由財産です。
YTOからのアドバイス
- 破産申立後に所有することが認められている自由財産は以下の通りです。
- 99万円以下の現金
- 破産後に取得した財産
- 法律で差押えが禁止されている財産
- 破産後の生活必需品
- 破産後の仕事に欠かせない道具類
- ただし自由財産の所有状況は破産申立時に破産管財人に報告する必要があります。
- 自由財産の準備状況を報告できるよう、事前に準備しておく必要があります。
ゼロゼロ融資とは…
- 新型コロナウイルス感染症の拡大で売上が減った企業を支援するための融資です。
- 金融機関に支払う利子を公的機関が3年間負担し、返済できない場合も信用保証協会が肩代わりする実質的に無利子(利子ゼロ)・無担保(担保ゼロ)の融資であることから「ゼロゼロ融資」と呼ばれます。
ゼロゼロ融資について知っておきたいこと
- ゼロゼロ融資は元金返済据置期間(最大5年)を設定でき、その間は元金返済の必要がなくなる融資です。
- ただし元金返済据置期間が満了した後、返済ができなくなり経営破綻につながることがあるので注意が必要です。
YTOからのアドバイス
- ゼロゼロ融資による借入は5年の元金据置期間が満了すると返済が始まります。
- 元金返済はかなり大きな負担となります
- ゼロゼロ融資を利用して返済能力以上の借入をしていた場合、据置期間満了による元金返済の負担から資金繰りが悪化して経営破綻となることがあります。
- その結果、倒産に追い込まれるケースも少なくありません。
- 注意が必要です。
損益計算書とは…
- 一定の決算期間内に①どれだけの利益が上がり、②どれだけの費用が出て、③どれくらいの利益になったかという財務状況を表す財務諸表のひとつです。
損益計算書について知っておきたいこと
- 破産申立時に破産管財人は直近2期分の決算書を必ず確認します。
- 特に決算の財務諸表である損益計算書を必ず確認します。
- 破産管財人は損益計算書により、一定期間で利益が上がったかどうかの状況を確認します。
YTOからのアドバイス
- 破産管財人は損益計算書から一定の決算期間内にどれだけの利益が上がったかを確認します。
- 直近2期分の損益計算書により利益が上がった事実を確認された場合、利益の使途も必ず確認します。
- 不適切な利益の使途があった場合、破産手続きで問題になることがあります。
- 注意が必要です。
総勘定元帳とは…
- すべての取引を勘定科目ごとに分類した会計帳簿のことです。
- 総勘定元帳は現金勘定や売上勘定などすべての勘定科目の記入欄が設けられている帳面です。
- 勘定科目ごとのすべての取引が記載された勘定口座を集めた会計帳簿で、仕訳帳とともに主要簿を構成するものです。
総勘定元帳について知っておきたいこと
- 総勘定元帳にもとづき、貸借対照表と損益計算書が作成されます。
- 総勘定元帳にもとづいた貸借対照表と損益計算書により、決算書(財務諸表)が構成されます。
YTOからのアドバイス
- 破産手続きにおいて破産管財人は直近2期分の決算書(財務諸表)を確認します。
- 粉飾決算等の不適切な会計処理をしている場合、破産管財人は総勘定元帳を確認します。
- 粉飾決算は総勘定元帳と貸借対照表・損益計算書の不一致により確認できます。
- 一線を越えた不適切な会計処理はこの確認により明らかになります。
- 注意が必要です。
- したがって一線を越えた不適切な会計処理を疑われた場合には総勘定元帳の提示を求められます。
- 破産手続きにおいて「総勘定元帳がありません」や「総勘定元帳を作成していません」は通用しません。
- 注意が必要です。
財産分与とは…
- 婚姻中に協力して蓄積した財産を、離婚の財産的効果として一方の者の請求により精算することです。
- 婚姻中に協力して蓄積した財産とはお金・購入財産等です。
財産分与について知っておきたいこと
- 会社倒産時に取締役なっている場合、財産分与された財産も破産の対象財産となってしまうことがあります。
- 離婚前に妻が会社負債の求償債務者となっている場合、財産分与により得た財産も破産の対象財産となってしまうことがあります。
- 注意が必要です。
YTOからのアドバイス
- 妻が取締役で会社の求償債務を負っている場合、離婚による財産分与で得た財産が破産の対象財産になってしまうことがあります。
- 離婚をしても会社の負債を免れることはできません。
- 会社の取締役になっていて会社の求償債務を負っている場合、離婚による財産分与で得た財産も破産の対象財産となってしまうことがあります。
- さらに妻個人名義の財産も破産の対象財産になります。
- 注意が必要です。
タップで発信アドバイザー直通電話